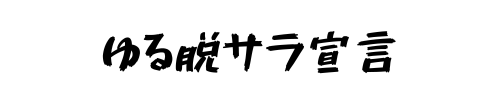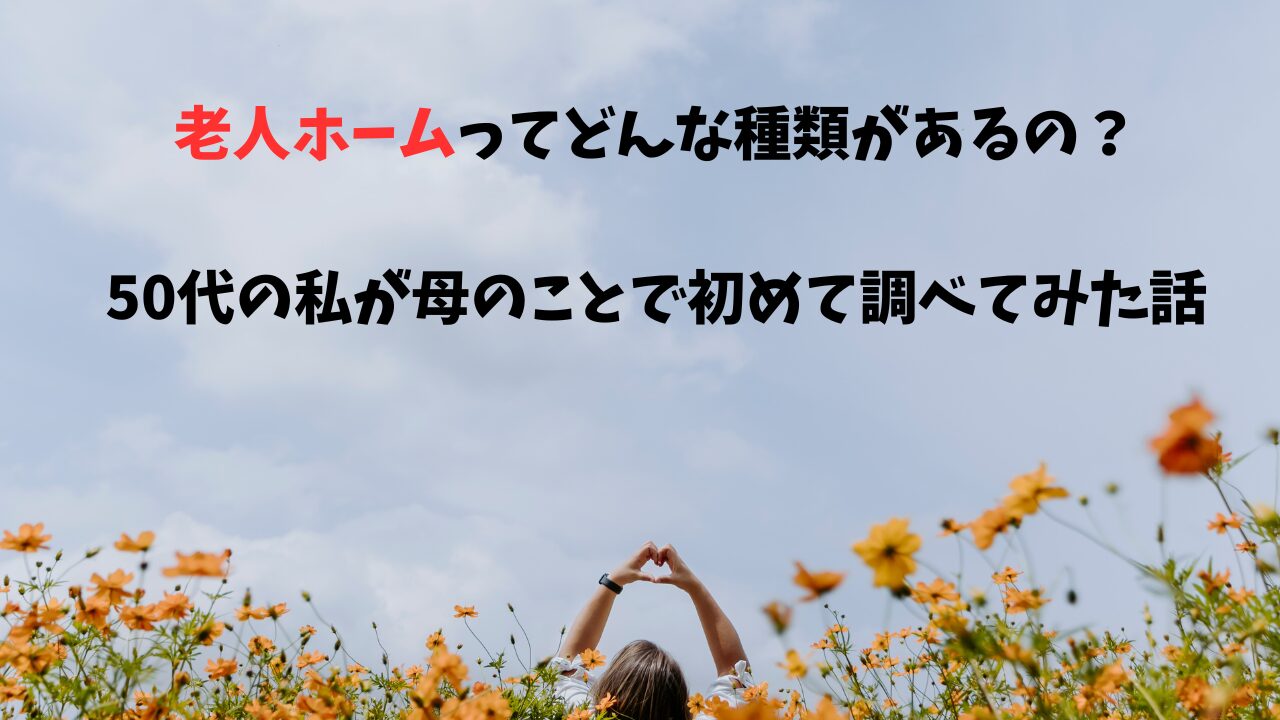最近、母の足の痛みをきっかけに、「そろそろ将来のことも考えておかないと…」と感じるようになりました。
まだ介護が必要な状態ではないけれど、もし何かあったとき、慌てずに対応できるようにしておきたい。
50代という年齢もあってか、自分自身の体力の変化や老後への不安も、少しずつ現実味を帯びてきました。
そこで、まずは「老人ホームにはどんな種類があるのか?」という基本から調べてみることに。
最初はまったくの無知でしたが、調べてみると意外と種類が多くてビックリ。
自立した人向け、介護が必要な人向け、医療ケアが必要な人向け…など、それぞれに特徴があることがわかってきました。
この記事では、私と同じようにこれから親のことを考えたいという方に向けて、老人ホームの基本的な種類や違いをわかりやすくまとめてみます。
- なぜ50代の私が、老人ホームについて調べ始めたのか
- 老人ホームの主な種類と、それぞれの特徴
- どんな人にどの施設が向いているのかの目安
- 実際に調べて感じた「気づき」や「今後の備え」について
そもそも、なぜ老人ホームについて調べ始めたのか?

きっかけは、84歳になる母の足の痛みでした。
これまで元気に一人暮らしをしていた母でしたが、最近「足が痛くて買い物に行くのがつらい」と話すことが増えてきて、少しずつ「老い」を意識するようになりました。
まだ介護が必要な状態ではないし、本人も施設に入るなんて考えていない様子。
でも、もしものときに備えて、選択肢だけでも知っておきたいという気持ちが芽生えたのです。
また、客室清掃の仕事を2年以上続けてきた中で、自分自身の体力の衰えも感じるようになってきました。
ふと、「親のことだけじゃなく、自分の将来もそろそろ考えたほうがいいのかも」と思ったのです。
最初は、「老人ホームって高いんでしょ?」とか、「そもそもどうやって選ぶの?」といった、漠然とした不安だけ。
でも調べ始めてみると、施設の種類や目的ごとに違いがあることがわかってきて、これは早めに知っておいたほうがいい情報だなと感じました。
老人ホームにはどんな種類があるの?|代表的な5タイプの特徴まとめ
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
特徴:
・バリアフリー対応の賃貸住宅
・基本的に自立または軽度の支援が必要な高齢者向け
・安否確認や生活相談のスタッフが常駐
・介護サービスは外部事業者と契約
向いている人:
・一人暮らしが不安になってきたけれど、まだ元気な人
・自由な生活を保ちながら、少しだけ見守りが欲しい人
住宅型有料老人ホーム
特徴:
・住まい+“食事・生活支援”がセットになった施設
・介護は外部の訪問介護サービスを利用(外付け)
・医療ケアが必要な場合は別途対応が必要
向いている人:
・日常生活は問題ないけれど、将来に備えて安心な環境を求める人
・一人暮らしに不安がある人
介護付き有料老人ホーム
特徴:
・施設内に介護スタッフが常駐し、要介護者を対象にケアを提供
・介護サービス費が包括的に含まれる(外部契約不要)
・24時間体制のところが多く、安心感が高い
向いている人:
・すでに介護が必要で、家族だけでは対応が難しい人
・要介護認定を受けている人
グループホーム
特徴:
・認知症の高齢者が、少人数で共同生活をする施設
・家庭的な雰囲気で、日常生活の延長のような暮らしができる
・原則、要支援2または要介護1以上+認知症の診断が必要
向いている人:
・認知症があり、家庭での生活が難しくなってきた人
・少人数で落ち着いた暮らしを希望する人
特別養護老人ホーム(特養)
特徴:
・公的施設で、費用が比較的安い
・要介護3以上の人が入所対象
・医療対応や看取りを行う施設もある
・ただし、入所待機者が多いのが難点
向いている人:
・重度の介護が必要で、経済的な負担を抑えたい人
・長期的な生活を前提とした場所を探している人
※これらは主なもので、まだまだこまかく種類があります。
私自身、「老人ホーム=高い・入りにくい」という先入観がありましたが、実は「元気なうちから入れる施設」もあることに驚きました。
実際に調べてみて思ったこと|50代の私の率直な感想
今回、「老人ホームの種類」を調べてみて、正直なところ──
こんなにいろいろあるのか…!と驚きました。
もともと私は、
「なんとなく「高い」イメージがある」
「介護が必要になったら、仕方なく入る場所」
そんな漠然としたイメージしか持っていませんでした。
でも、実際に情報を集めてみると、次のようなことを強く感じました。
「どれが合うか」は、親の性格・健康状態・お金の事情で変わる
たとえば――
✔ 体は元気だけど、一人暮らしが心配なら「サ高住」や「住宅型」が向いている
✔ 認知症が進んできたら「グループホーム」が選択肢になる
✔ お金に余裕がない場合は「特養」も検討すべき
つまり、「正解」は人それぞれで、ケースバイケース。
だからこそ、選ぶにはある程度の知識と事前の備えが必要だなと感じました。
施設ごとに本当に雰囲気が違う(見学の必要性を実感)
ネットで調べただけでも、
「ここは自由な雰囲気」
「ここは医療体制がしっかり」
「この施設は評判がよさそう」
など、かなり印象が違います。
これは実際に「見て・聞いて・感じる」しかない。
見学してみないと分からない空気感って、絶対にあると思いました。
自分の老後についても、考えるようになった
今回、母のことをきっかけに調べ始めたのですが、
気づけば自分の老後も頭に浮かぶように。
「もし一人暮らしで倒れたらどうなる?」
「いずれは自分も、どこかに入るのか?」
「そのとき、いくらかかる? どんな施設がある?」
親のこと=未来の自分のことでもある──
そんな実感がじわじわと湧いてきました。
知ることは、備えること
正直、まだ母は元気で、すぐに何か決断しなければいけないわけではありません。
でも、今回のように「少しずつ知っておくこと」が、将来の備えになる**と感じました。
焦らなくていいけれど、何も知らないままでいるのはもっと不安。
だからこそ、これからも「見学」や「費用感」など、少しずつ情報を整理していきたいと思っています。
まとめ|「まだ先のこと」と思っていたけれど、調べてよかった

今回、母のことをきっかけに老人ホームの種類を調べてみて、
「まだ早いかな?」と思っていた自分の意識が少し変わりました。
たしかに、今すぐ必要というわけではありません。
でも、知っておくだけで安心感が全然ちがう。
そして、これは「親のこと」だけでなく、「自分のこれから」にもつながっています。
- 50代という年齢は、「老後を考えはじめる」にはちょうどいいタイミング
- 元気な今だからこそ、冷静に選択肢を整理できる
- 家族や自分の将来を、少しずつ整えていくことができる
次回は、いよいよ「実際に見学する施設を選ぶポイント」について調べてみる予定です。
もし、同じように「親のことが少し気になってきた」「何から始めればいいか分からない」という方がいれば、
一緒に少しずつ「備え」を進めていけたらうれしいです。